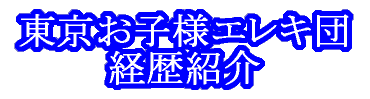
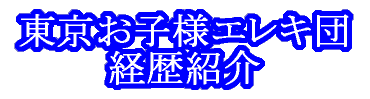 |
東京お子様エレキ団 |
 1980年代に入った頃、高校生の私は、当時まだ隔週金曜日発売だった「ぴあ」を毎号欠かさず買っていた。そして、それこそ隅から隅まで、くまなく読んでいたものだ。その中にライブスポットのページがあったのだが、四谷フォーバレーや渋谷Egg-manのスケジュールに、しばしば登場するバンドがあった。それが、「東京お子様エレキ団」である。もちろん、演奏は聴いたこともない。でも、なんとも言えないセンスのバンド名に、心惹かれるものがあった。 1980年代に入った頃、高校生の私は、当時まだ隔週金曜日発売だった「ぴあ」を毎号欠かさず買っていた。そして、それこそ隅から隅まで、くまなく読んでいたものだ。その中にライブスポットのページがあったのだが、四谷フォーバレーや渋谷Egg-manのスケジュールに、しばしば登場するバンドがあった。それが、「東京お子様エレキ団」である。もちろん、演奏は聴いたこともない。でも、なんとも言えないセンスのバンド名に、心惹かれるものがあった。エレキ団は、ボーカルの阪口あやとギターのポーク林とで結成された。他のパートは、何度かメンバーチェンジしている模様。最初は、シーナ&ロケットとかサディスティック・ミカ・バンドのコピーを演っていたが、次第にオリジナルへ移行していったようだ。バンド編成も、ギターが2本いたり、キーボードが1本だったり2本だったりと、けっこう変化しているらしい。 レパートリーは、時期によってかなり変わっている模様である。基本的にポップなのだが、俗に言うポップスという類ではない。GENESISなどプログレからのパクリねたに近いアイデアや部分的なアレンジの流用も多いが、いい部分をもってきてツボを抑えてるので、実にコンパクトだが有機的なアレンジとなっていた。いわゆる歌謡曲の「ハコBAND臭い」演奏が、なんとも魅力的であった。 |
東京お子様エレキ団の |
エレキ団を語る上で欠かせないのが、当時のミュージックシーンであろう。 1984年当時は、いわゆるインディーズブームの到来間近という時期で、シーンは大いなる上昇傾向にあった。 インディーズというと、現在ではむしろプロレスや映画に多く用いられる言葉であるが、音楽の場合には「既存の流通経路に乗せない(いわゆる手売り・委託販売主体の)自主制作レコード」という意味である。古くは東京ロッカーズなどが活躍した1970年代後半、むしろそれ以前から「自主制作レコード」というものは存在していたが、スターリン・水玉消防団などのレコードが驚異的な売り上げを記録するにしたがって、注目されるようになってきた。 その時期に元スターリンのギタリストであった田村氏が、自主レーベル「ADKレコード」を設立するにあたり、「インディーズ」という言葉を初めて使用したように記憶している。しかしながら、1970年代のロンドンのミュージックシーンがそうであったように、パンク系の音楽が主体であり、「インディーズ=パンク」もしくは「インディーズ=暗くマニアックな音楽」という傾向は否めなかった。 そんな中で異彩を放ったのが、有頂天のボーカリスト小林(ケラ)氏の主宰する「ナゴムレコード」であった。パンクでないポップでシュールなバンドを中心としたリリースを続け、インディーズブームの立役者であったことは誰も否定できないであろう。インディーズブームの終焉に向けて、数々のバンドがメジャーデビューを果たし、そのほとんどが自然消滅していく中で、「ナゴムレコード」出身のアーティストが現在でも広く活躍しているのは注目される。 「筋肉少女帯」はバンド活動はもとより、大槻氏のコラムニストとしての露出度が顕著である。性格俳優として売り出し中の田口トモロヲ氏も、「ばちかぶり」というバンド名義でレコードを数枚リリースし好セールスを記録している。現在人気の高い「電気グルーヴ」も、前身の「人生」というユニットで作品を発表している。 そんな「ナゴムレコード」の小林氏が中心となってFM東京(当時)でオンエアされたのが「FMフレッシュウェイブ〜やっぱり楽しいインディーズのクリスマス」(1983年12月21日)である。内容的には他愛のないものであったが、当時の明るい系インディーズのパワーを感じることができた。 さて、その中に登場したのが、「東京お子様エレキ団」である。名前は何度か聞いたことはあったが、曲を耳にするのは初めてであった。オンエアされた「秘密の水曜日」は、個人的に嗜好しているシャッフル系のビートが心地よく、そこにボーカルの阪口あや嬢の歌声が妙にマッチしていて、一発で好きになってしまった。 しばらくはその番組で録音した曲を繰り返し聴くのみであったが、やはりライブを観たくなり「ライブ in MURASAKI」へ連れ立ったのであった。 |
私と |
そんなわけで、「FMフレッシュウェイブ」をきっかけに好きになり、「ライブ in MURASAKI」で初めて観て、たちまちとりこになってしまった。当時学生だった私は、同じ音楽サークルのやつらとライブに行ったが、若気の至りで「あやちゃ〜ん!」などと声援したりなんかして今思うとちょっと恥ずかしい。でもそのせいか、ライブ後にあやさんと話をさせてもらったりして、嬉しかった記憶がある。 結局、ライブは4回しか観れず、エレキ団は解散してしまった。解散後は、ライブ録音したテープをひたすら聴き続けるしかなかった。でも、その数年後、私はメンバーを集めてコピーバンドを結成したのであった。バンド名は、「東京おニャンコえれき団」。男4人、女3人の大所帯。お医者さんや看護婦さんや、セーラールックとか、ビジュアル的にもイケてるバンドだったと思う。 |
メンバー紹介 |
ボーカル担当。本名:阪口 文(さかぐち あや)。後に結婚し、二川 文(ふたがわ あや)となる。 |
 |